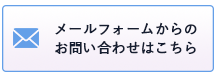【相続放棄】
最高裁による3ヶ月の起算点の修正(最判昭59.4.27)
熟慮期間の起算点について、この最高裁判例が出るまでは「被相続人の死亡を知り、かつ、自己が法律上相続人となった事実を合わせて知ったとき」(相続人覚知時説)が熟慮期間の起算点であるとするのが最高裁であった。
※当時から家裁や下級審においてはより柔軟に運用する動きがあった。
社会の変化に伴い、それでは救済できない事例が増加していった。
【連帯保証】
〈事案概要〉(最判昭59.4.27)
- 父A(被相続に人)のギャンブルが原因で、妻Bと子C・D・E(相続人ら)は家を出た。
- その後程なくして妻Bは離婚。それ以降、Aが亡くなる直前まで子C・D・Eとは一切交流がなかった。
- 父Aはその後、生活保護を受けながら単身アパートで暮らしていた。
- そんな中、家族が家をでて10年程たった時期に、父Aは、知人Yの債務を保証するために債権者Xとの間で連帯保証契約を結んだ。
- その後、父Aは病気で入院、余命わずかとなり、そんな中、Cは民生委員から父Aの状況を知らされる。
- Cは、父Aが亡くなるまでの間、3度ほどお見舞いに行ったが、負債の話は一切出なかった。
- その後、父AはCに看取られ病院で死亡した。D・EもすぐにCより父Aの死亡を知らされた。
- 当時、父Aには相続すべき積極財産が全くなく、Aの葬儀も行われず、遺骨はそのまま寺に預けられた。
- その後、父Aが死亡して1年近く経ったころ、債権者Xから相続人C・D・Eに対し突然の請求がきた。
- C・D・Eは、すぐに大阪家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、家庭裁判所はこれを受理した。
- 債権者Xは、本件受理の効力を裁判で争った。
この裁判で最高裁は、従来通りの「相続人覚知時説」を原則としながらも、一定の事情により起算日の例外を認める、いわゆる「起算日例外説」を新たに打ち出した。
一定の事情とは、
- 被相続人に相続財産(債務を含む)が全く存在しないと信じたこと。
- 相続人において上記のように信じるについて相当な理由がある。
- 相続人において相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったこと。
- これで従来の起算点よりも柔軟に解釈されることとなったものの、あくまで最高裁は「被相続人に相続財産(債務を含む)が全く存在しないと信じた場合に限る」とする限定説に立っているとされており、以降の最高裁の判例においても限定説が貫かれている。
・最決平13.10.30
・裁決平14.4.26
- これについては、学説上反対意見もあり、
「一部相続財産の存在は知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう「債務が存在しない」と信じた場合」も含まれるべきである。
(非限定説)
とする考え方もあります。
【重要】
- 確かに最高裁は限定説をとり例外を厳格に解釈している。
しかしながら、下級審の裁判や家裁の実務は一部相続財産の認識があった場合においても「非限定説」の解釈を基に、相続放棄の受理を柔軟に認めている。